予防接種健康被害制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに救済が受けられます。
予防接種後に健康被害が生じた場合、その接種が予防接種法による定期接種か予防接種法に基づかない任意接種かによって、適用される救済制度が異なります。なお、それぞれの制度によって請求期限が異なりますのでご注意ください。
定期予防接種による健康被害の救済制度
予防接種法による「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。
救済制度では、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種に基づく健康被害救済制度による救済給付が行われます。なお、請求は、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に請求することになります。
詳しくは、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度について」のホームページをご覧ください。
▶予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
任意接種による健康被害の救済制度
予防接種法に基づかない任意の予防接種(定期予防接種の対象年齢からはずれた場合や、接種を受ける期間を過ぎた場合など)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます。
給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
なお、救済の対象や支給額は予防接種法によるものと異なります。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へご相談ください。
▶医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルスワクチン接種による場合
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる制度が異なります。相談及び申請窓口は、下記図をご参照のうえ、各請求窓口へお問い合わせください。

(第32回自治体説明会より抜粋)
「医療費・医療手当」の請求においては、医療機関等において受診証明書を作成いただくことになります。
受診証明書の作成にあたり、記載方法及び注意点等をまとめたマニュアル(医療機関向け)をご活用ください。
新型コロナワクチンに係る健康被害救済制度「受診証明書」記載マニュアル (PDFファイル: 1.6MB)
申請にあたって
・一般的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を拒むものではありません。)。
・必要書類(受診証明書や診療録等)の作成に文書料がかかる場合がありますが、費用はすべて申請者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。
・医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合もあります。
・申請を受けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な書類を追加で提出していただく場合があります。持病がある方や健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関からも提出していただく場合があります。
・国の審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します。
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
〒817-1292
対馬市豊玉町仁位380番地
電話番号:0920-58-1116
ファックス番号:0920-58-2755
メールフォームからお問い合わせをする













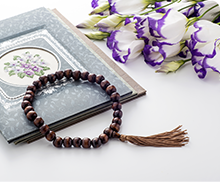









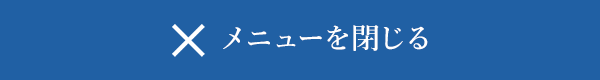



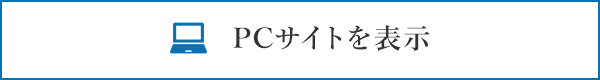
更新日:2025年04月01日