対馬沿岸の藻場の減少
対馬沿岸の藻場の減少
かつて海底が見えないほど、船が通れないほどあったという藻場が今、消滅の危機にあります。
対馬沿岸では、1980年代から各地で藻場の衰退や消失が報告されるようになりました。当初は密漁が疑われるほど海藻が急減した地域もあったようです。
その後も藻場が衰退・消失する範囲は拡大し続け、現在ではほぼ全域に広がっています。
その理由には様々な説がありますが、
-
海洋熱波と呼ばれる高水温の継続による衰弱・枯死
-
大型台風等の波浪による流失
-
海藻を食べる生物による過度な食圧(食害)
-
泥などの堆積や、他の固着性生物との競合による生息適地の減少
-
栄養不足や有害物質の影響による生長阻害
などによって海中の“食う-食われる”のバランスが崩れたことが原因ではないかと考えられています。
また、これらの要因は複雑に作用し合っている可能性もあり、その対策を難しくしています。
上記の理由などによって海藻が消滅する現象は「磯焼け」と呼ばれ、海底には文字通り焼け野原のような光景が広がります。
磯焼けの定義
「浅海の岩礁・転石域において、海藻の群落(藻場)が季節的消長や多少の経年変化の範囲を
超えて著しく衰退または消失して貧植生状態となる現象」(藤田,2002)



葉状部が欠損し、”茎”だけになったカジメ

大型海藻が消失し、焼け野原のようになった海底

以前から対馬沿岸に生息するノトイスズミ。近年では“食害生物”とされる。
この記事に関するお問い合わせ先
水産課
〒817-8510
対馬市厳原町国分1441番地
電話番号:0920-53-6216
ファックス番号:0920-53-6122
メールフォームからお問い合わせをする
- みなさまのご意見をお聞かせください
-













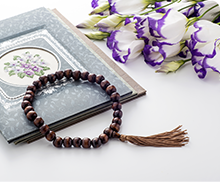









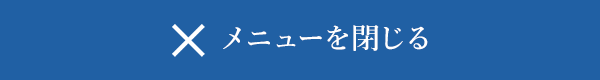



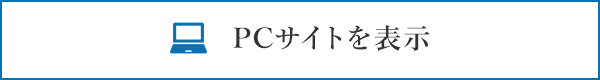
更新日:2024年04月12日